世界中で愛されている「寿司」は、日本の誇るグルメのひとつ。
見た目も美しく、味わいも奥深いこの料理には、長い歴史と豊かなバリエーションがあります。
ここでは、寿司の魅力をより深く知ってもらえるよう、基本からマナーまで幅広く紹介していきます。
寿司について

寿司は、日本の食文化を代表する料理です。酢飯に新鮮な魚介や野菜などを組み合わせ、見た目にも美しく、味わい深い一品に仕上がっています。
「寿司=生の魚」というイメージが強いかもしれませんが、実は具材の種類はとても豊富。マグロやサーモンなどの刺身系だけでなく、卵焼き、きゅうり、エビフライなども寿司ネタとして親しまれています。
手軽に食べられるのに華やかで、少し特別な感じがある寿司は、普段の食事からお祝いの席まで、幅広いシーンで楽しまれています。まさに「ザ・日本食」と言える存在です。
TasteTune「Sushi」
ところで皆さん、tastetuneの音楽「Sushi」はお聞きになりましたか?
料理をよりおいしく食べるために、多くの人に知ってもらうために音楽として公開するということが、このtastetuneの根幹をなしています。
ここでは、この音楽に込められた思いや表現、工夫をご紹介します。
音色に込めた思い
「Sushi」の根底にあるのは、伝統的な日本の楽器と現代的な雰囲気の音の絶妙な融合です。箏の優雅な響き、尺八の奥深い音色を使用し、まるでシャリとネタのような完璧なバランスを表現しました。
職人の技をリズムで表現
この曲のリズムには、寿司職人の手さばきを重ねています。丁寧で正確で、優雅な動きが音になっていて、一音一音がまるで一貫の寿司のように感じられるようにしました。耳を澄ませると、職人の集中や息遣いまで伝わると思います。
五感を呼び起こす音の工夫
曲の中には、巻き簾を軽く叩く音や、包丁が刺身を切るときの小さな音などを入れて、寿司を作る過程を音で描きました。全体を通して「新鮮さ」「シンプルさ」「純粋さ」を大事にしています。深い海のような響きはネタの新鮮さを、鋭い音のアクセントはわさびの刺激を表しています。
一口ずつ味わうような音楽
「Sushi」という曲は、一音一音を一貫の寿司のように味わえる音楽です。フレーズの流れはうま味の波のように広がり、耳と心で寿司を楽しめる体験を目指しました。
穏やかで優雅な時間
全体を通して、この曲は「穏やかで優雅で、心が深く入り込める」時間を作り出します。寿司を食べる時の静かで満たされた気持ち、日本らしい美しさを音で表現しました。目を閉じて聴けば、寿司を音で味わう体験を楽しんでいただけると思います。
寿司の味
寿司といえばやはりその寿司ネタの数!
日本に住んでいる筆者でさえその数はほとんど把握できないほどです。
今回はその中からメジャーなマグロをご紹介します。
マグロ
寿司といえばこれ!
子どもには特に人気な一皿だと思います。
マグロの中にも大トロ、中トロ、赤身など部位によって味わいも変わってきます。
まずは大トロ!
大トロはマグロの最も脂ののった腹側の部位で、淡いピンク色をしています。
金城にあばらが混ざっており、表面はつやつやで光沢が輝いています。
触感も口に入れた瞬間からとろけるような柔らかさと旨味が口いっぱいに広がってきます。
つぎに中トロ!
簡単に表現すると大トロと赤身の中間に位置するといっていいでしょう。
大トロの淡いピンク色と赤身の赤色が入り混じった色をしています。
脂がのりつつも赤身の部分も残っている中トロは、脂っこいものが苦手な方も楽しむことができます。
一貫食べるなら大トロ、たくさん食べるなら中トロといわれることもあります。
最後に赤身!
脂が少ないため引き締まっており、鮮やかな赤色をしています。
マグロ本来のミネラルや鉄分といった旨味を感じることができ、咀嚼するごとにその旨味を感じることができる噛み応えのある肉質が特徴です。
寿司の定番といえばこれ!幅広い層に楽しまれる寿司界の王様です。
寿司の歴史について
起源は“保存食”だった
寿司の起源は、東南アジアにおける魚の保存方法にあります。
「なれずし」と呼ばれるスタイルは、魚を塩とご飯で漬け込み、発酵させて保存するというもので、現在の寿司とはかなり異なるものでした。
このなれずしが中国を経由して日本に伝わり、やがて独自の進化を遂げていきます。
江戸時代に“握り寿司”が誕生

江戸時代になると、発酵を必要としない「早ずし」が登場し、さらに酢飯と新鮮な魚をその場で握って出す「にぎり寿司」が生まれます。
このにぎり寿司は、江戸の町で屋台スタイルの“ファストフード”として爆発的な人気を集めました。手軽に食べられて、しかも美味しいということで、多くの庶民の間で愛される料理となったのです。
現代では世界中で愛される料理に

現代の寿司は、時代とともに進化し、日本国内のみならず世界中に広がっています。
特にアメリカを中心にブームとなった「カリフォルニアロール」など、海外で生まれたユニークな寿司スタイルも注目を集めています。
今では「SUSHI」は世界共通語となり、日本の伝統を受け継ぎながらも、国境を越えて人々を魅了し続ける料理へと成長しました。
寿司の食べ方とマナーについて
寿司は高級店でもカジュアルなお店でも楽しめる料理ですが、ちょっとしたマナーを知っておくと、よりスマートに味わえます。
ここでは、初心者でも安心して楽しめる、基本の食べ方とマナーをご紹介します。
1. 手で食べてもOK!
寿司は手でつまんで食べるのが伝統的なスタイル。特に「にぎり寿司」は、手で食べてもまったく問題ありません。
もちろん、箸を使っても大丈夫です。自分が食べやすい方法で、リラックスして楽しみましょう。
2. 醤油はネタ側に少しだけつける
にぎり寿司に醤油をつける際は、ネタの面を下にして軽くつけるのが基本です。
シャリ(ごはん)側に醤油をつけると、形が崩れてしまったり、味が濃くなりすぎたりすることがあります。
また、軍艦巻きのように醤油をつけにくい形の寿司には、ガリ(しょうが)を使って少しだけ醤油をのせる方法もあります。
3. ガリは「口直し」として活用

ガリは寿司と一緒に食べるものではなく、異なる種類の寿司を食べる合間に「口直し」として食べるのが本来の使い方です。
口の中をさっぱりさせて、次のネタの味をしっかり楽しむことができます。
4. あがり(お茶)で口の中をリセット
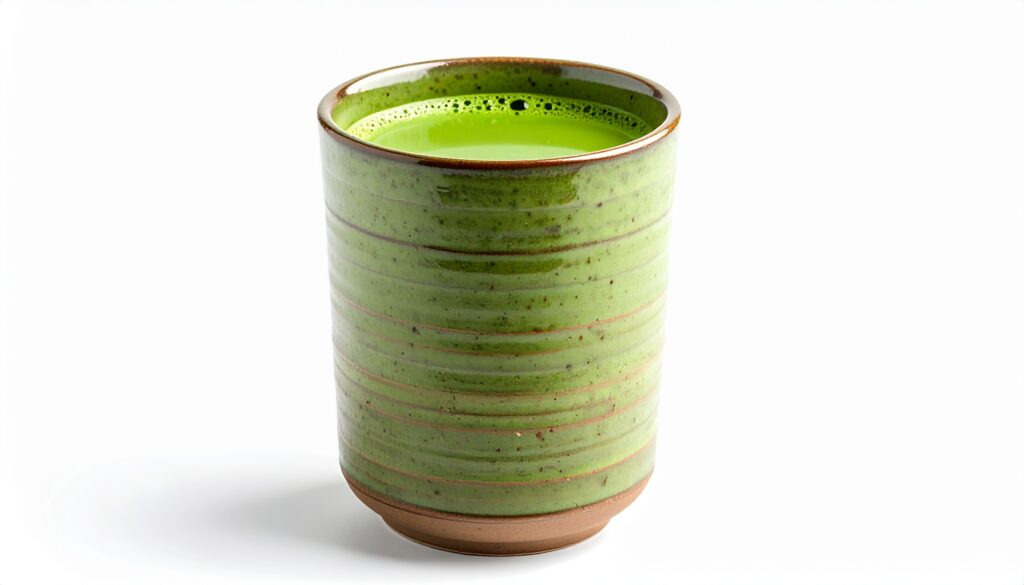
寿司屋で出される熱いお茶は「あがり」と呼ばれ、脂っこいネタを食べた後などに口をさっぱりさせる役目があります。
口直しのガリと比べ、あがりは食事中でも食後でも自由に飲んでOKです。
気分をリフレッシュさせながら、お寿司をゆったり味わいましょう。
5. 食べる順番は「淡白なネタから濃厚なネタへ」
美味しく寿司を楽しむためには、味の順番にも少し気を配ってみましょう。
白身魚や貝類などのあっさりしたネタから、トロやウニ、イクラなどの濃厚なネタへと進むと、味の変化をしっかり感じられます。
これは厳密なマナーというより「通な楽しみ方」のひとつです。
6. やってしまいがちなNGマナー
楽しむうえで、以下のような行動は避けたほうが良いとされています。
- 醤油をたっぷりつけすぎる
- ガリをのせて食べる
- シャリだけ残す
- 高級店でスマホで写真を撮り続ける
職人さんや他のお客さんへの配慮を忘れず、静かに楽しむのが大人のマナーです。
ただし、回転寿司などのカジュアルなお店では、そこまで堅苦しく考える必要はありません。
ちょっとした気配りとリスペクトがあれば、誰でも楽しく寿司を味わうことができます。
寿司の作り方
自宅でも挑戦してみたい!という人のために、シンプルな寿司の作り方を紹介します。
本格的な職人技がなくても、美味しく楽しめる方法がたくさんありますよ。
◆ 基本の酢飯の作り方
寿司づくりの土台になるのが「酢飯」です。
材料(2〜3人分)
- ごはん(炊きたて):2合
- 酢:大さじ3
- 砂糖:大さじ2
- 塩:小さじ1
手順
- 酢・砂糖・塩をよく混ぜて「寿司酢」を作ります。
- 炊き上がったごはんを大きめのボウルに移し、寿司酢を全体にかけます。
- 切るように混ぜながら、うちわなどで冷ましてツヤを出せば完成!
◆ 代表的な寿司の作り方例
にぎり寿司
- 酢飯を一口大に握って土台を作る(ふんわりがコツ)
- 好みのネタ(刺身用のマグロやサーモンなど)を乗せる
- わさびを少量はさむのも◎
巻き寿司(のり巻き)
- 巻きすの上に海苔を敷き、酢飯を広げる(全体に均等に)
- 中央に具材(きゅうり、玉子、カニカマなど)をのせる
- 巻きすを使ってくるくる巻き、少し置いてなじませてから切る
手巻き寿司(パーティーに人気)
- 海苔を1/4サイズほどに切る
- 酢飯と好きな具材を乗せて、くるっと巻く
- 好きな組み合わせで自由に楽しめる
◆ ポイント
- ネタは新鮮さが命!スーパーなどでも「刺身用」の表示を確認しましょう。
- しゃり(酢飯)は強く握らないのがコツ。ふんわり軽い口当たりになります。
- お酢の風味が飛ばないよう、冷蔵庫には入れすぎないのが◎
まとめ

寿司は、長い歴史と深い文化を持ちつつも、誰でも気軽に楽しめる日本料理です。
基本的な知識やマナーを知っておくだけで、魅力はさらに広がります。
日常の中でも、特別な日でも。ぜひ寿司を通して、日本の食文化の奥深さを体験してみてください。










コメント
コメント一覧 (1件)
日本の料理である寿司を紹介しているだけではなく、曲として寿司を表現しているのがとっても面白いと思った。
マグロを主に紹介していたが、寿司屋ではえびとラーメンしか食べない僕にとっては、えびも紹介して欲しかった。